去年の1月にぼくはある企画を出してボツになった。でも、さほど思い入れもなかったので、そんなものかな、と思って、落ちたことも忘れていた。で春頃、後輩に何となく、こんな企画を出して落ちたんだよね、って話をしたら後輩が「その企画、ちょっとだけ書き直して連名で出していいですか?」と言うので、いいよ、どうせ落ちた企画だし、なんて言ってたら、あれよあれよと試作品制作、より大がかりなテスト作品作成と進んで、いよいよこの春大々的に世に出ることになった。いい話!…なんだけど、なんか一連のこの感じが、ぼくの最近の体たらくを象徴している気がする。
問題点は3つ。
1)どっかズレてる。でも自分ではどこがズレてるのかわからない。
たぶん後輩には、それがわかった。だから、矯正することが出来た。
2)どうしてもこの企画を通そう!という気概がない。
後輩は、企画選定者と何度も飲みに行ったりコミュニケーションを取って、
ねばり強く企画を成立させていった。ぼくはあっさり捨てた。
3)というようなことに関して、ぼくには何の感情も沸いてこない。
悔しくもないし、逆にうれしくもない。これは何なんだろう…。
つきつめてゆくとこれらのマイナス点は、ぼくが自分の感情の振れ幅、特に大きく負に触れた時の自分の感情を、ひとりでコントロールできないということから生じている気がする。なので、気持ちを切り替える意味で、ピーター・ゲイの「官能教育」(みすず書房)を読み始めました。この本は、19世紀ブルジョアジーたちが、いかに「性愛」というものの「正しさ」の概念を革命的に変えていったか、を精神分析学に依拠して読み取ってゆこう、という本らしいので、一度きちんと読んでみたくて。あと楽しそうだし。「メイベル・ドットの奔放な性愛記録の分析から、精神と現実世界が対峙する場としての「無意識」の力を解明する」という帯にも魅かれました。これから読み進めたいと思います。
問題点は3つ。
1)どっかズレてる。でも自分ではどこがズレてるのかわからない。
たぶん後輩には、それがわかった。だから、矯正することが出来た。
2)どうしてもこの企画を通そう!という気概がない。
後輩は、企画選定者と何度も飲みに行ったりコミュニケーションを取って、
ねばり強く企画を成立させていった。ぼくはあっさり捨てた。
3)というようなことに関して、ぼくには何の感情も沸いてこない。
悔しくもないし、逆にうれしくもない。これは何なんだろう…。
つきつめてゆくとこれらのマイナス点は、ぼくが自分の感情の振れ幅、特に大きく負に触れた時の自分の感情を、ひとりでコントロールできないということから生じている気がする。なので、気持ちを切り替える意味で、ピーター・ゲイの「官能教育」(みすず書房)を読み始めました。この本は、19世紀ブルジョアジーたちが、いかに「性愛」というものの「正しさ」の概念を革命的に変えていったか、を精神分析学に依拠して読み取ってゆこう、という本らしいので、一度きちんと読んでみたくて。あと楽しそうだし。「メイベル・ドットの奔放な性愛記録の分析から、精神と現実世界が対峙する場としての「無意識」の力を解明する」という帯にも魅かれました。これから読み進めたいと思います。

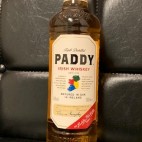
コメント