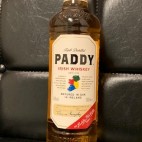「家政婦のミタ」を見返していて思ったんだけど、いまどき視聴率40パーセントをとるコンテンツにはたぶん集合無意識を揺るがすほどの大きな「力」が秘められていたはずで、ミタのその「力」というのは、もしかしたら、日本で(ほぼ)初めて、「母の不在」を描くことに成功した、というところにあるのではないか、と思った。
さっき読み終えたブローティガンの「バビロンを夢見て」もそうだけど、物語で描かれる家族はたいていどこかが「失われて」いる。それは「誰か」だったり「関係そのもの」だったりするけれど、最も多く描かれてきたのは「父の不在の物語」だったと思う。
日本文学の歴史は「父(の不在)を描くことの歴史」だった気がするし、「バビロン」もそうだけど、アメリカ文学だって繰り返しその主題を描いてきた、でも、「ミタ」は、どんな小説も描き切れなかった「母の不在」を描き切った。
「夫が愛してくれなかったから自殺した」という「母」は、「実在」としても失われているし、また、「概念」としても失われている。「ミタ」は最初から最後まで、母を「なきもの」として扱う。そして最後の最後まで、「ミタ」は母の代役を引き受けようとはしない。なぜなら、「母」は幻影に過ぎないから。我々はこれからみんな、「母」のいない時代を生きなければならないのだから。
おそらく、このドラマを見るまでにも、誰もがどこかでうすうす感じていたんだと思う、でも、「ミタ」は、みんながうすうす感じていたことを具現化した。それを一言でいいあらわせば、そしてニーチェが「神は死んだ」という言い方をもじって言えばこうなる。
「母は死んだ」。
「ミタ」というのは、そういうドラマだったと思う。
さっき読み終えたブローティガンの「バビロンを夢見て」もそうだけど、物語で描かれる家族はたいていどこかが「失われて」いる。それは「誰か」だったり「関係そのもの」だったりするけれど、最も多く描かれてきたのは「父の不在の物語」だったと思う。
日本文学の歴史は「父(の不在)を描くことの歴史」だった気がするし、「バビロン」もそうだけど、アメリカ文学だって繰り返しその主題を描いてきた、でも、「ミタ」は、どんな小説も描き切れなかった「母の不在」を描き切った。
「夫が愛してくれなかったから自殺した」という「母」は、「実在」としても失われているし、また、「概念」としても失われている。「ミタ」は最初から最後まで、母を「なきもの」として扱う。そして最後の最後まで、「ミタ」は母の代役を引き受けようとはしない。なぜなら、「母」は幻影に過ぎないから。我々はこれからみんな、「母」のいない時代を生きなければならないのだから。
おそらく、このドラマを見るまでにも、誰もがどこかでうすうす感じていたんだと思う、でも、「ミタ」は、みんながうすうす感じていたことを具現化した。それを一言でいいあらわせば、そしてニーチェが「神は死んだ」という言い方をもじって言えばこうなる。
「母は死んだ」。
「ミタ」というのは、そういうドラマだったと思う。