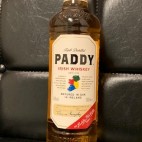なんかいま、いい感じに不幸だな。
でも、幸福、っていったい何だろう。
こうして夜中、仕事を終えてひとり家にいると、
ああ、絶望的にひとりだ、と思う。
でもそれは、自分で選んだことなんだ。
それを不幸と呼ぶのは、おこがましい気がする。
すべてのことに意味がある、としたら、
いまこうしていることに、いったい何の意味があるんだろう。
差し伸べてくれた、たくさんの手をふりはらって、
こうしてここにいることに、何かの意味があるんだろうか。
あるの?本当に?
ひしひしと、少しずつ切り裂かれ始めている気がする。
でも、幸福、っていったい何だろう。
こうして夜中、仕事を終えてひとり家にいると、
ああ、絶望的にひとりだ、と思う。
でもそれは、自分で選んだことなんだ。
それを不幸と呼ぶのは、おこがましい気がする。
すべてのことに意味がある、としたら、
いまこうしていることに、いったい何の意味があるんだろう。
差し伸べてくれた、たくさんの手をふりはらって、
こうしてここにいることに、何かの意味があるんだろうか。
あるの?本当に?
ひしひしと、少しずつ切り裂かれ始めている気がする。
疲れた、っていうか疲れてる。
「きょうは天気がよくて吐きそうです亅
って書いた、吉高由里子の気持ちがわかるような気がする…。
久しぶりに中野に行きます。
なんか故郷に帰る気分。
別に住んでたわけでもないのに、
そこに昔の自分がいる気がする。
友だちに「サドが面白い!亅って熱く語られたので
読もうかと思うんだけど、何から読めばいいんだろう。
「悪徳の栄え亅?「閨房の哲学亅?
悩んでます…。
「ソドム亅は高校時代に読んで
ついていけなかった憶えがあります。
童貞だったしな…。
ああ、空が青い。
「きょうは天気がよくて吐きそうです亅
って書いた、吉高由里子の気持ちがわかるような気がする…。
久しぶりに中野に行きます。
なんか故郷に帰る気分。
別に住んでたわけでもないのに、
そこに昔の自分がいる気がする。
友だちに「サドが面白い!亅って熱く語られたので
読もうかと思うんだけど、何から読めばいいんだろう。
「悪徳の栄え亅?「閨房の哲学亅?
悩んでます…。
「ソドム亅は高校時代に読んで
ついていけなかった憶えがあります。
童貞だったしな…。
ああ、空が青い。
自分でもわからない。
たぶん、光だけ見て暮らすことも出来た。
なのに、どうして闇の方に魅かれるんだろう。
どうして。
アメリカのディズニーランドの「白雪姫」の館では、
入ってすぐ二階の窓に「白雪姫のまま母」が現れ、
観客ひとりひとりに何かをささやいて消えるという。
ほとんどの観客が気づかずに通り過ぎるこの仕掛けは、
ウオルト・ディズニーが強くこだわったアイデアだった。
まま母は何をしているのか。
彼女は、訪れる客ひとりひとりに、呪いをかけているのだ。
たぶんウオルト・ディズニーは、
闇があるから、光がより輝いて見える、ということを知っていた。
それと同じことをぼくは望んでいるんだろうか。
最後に光のほうへ行くため、敢えていま、闇の中を歩こうと?
ベアトリーチェに導かれたダンテのように?
そうじゃない気がするんだよね。
ぼくはたぶん、光より闇に、調和より混沌に魅かれている。
それは親のせいでも、誰かのせいでもなく、ぼく自身の「性」のせいだ。
認めなければ。
けれど、心のどこかで期待している。
この「闇」が、「世界」を作り変えることを。
あるいは、より「完全」なものにすることを。
ぼく自身の「世界」を。
そういえば6月に公開される「光のほうへ」は面白そうです。
見てみたい。
たぶん、光だけ見て暮らすことも出来た。
なのに、どうして闇の方に魅かれるんだろう。
どうして。
アメリカのディズニーランドの「白雪姫」の館では、
入ってすぐ二階の窓に「白雪姫のまま母」が現れ、
観客ひとりひとりに何かをささやいて消えるという。
ほとんどの観客が気づかずに通り過ぎるこの仕掛けは、
ウオルト・ディズニーが強くこだわったアイデアだった。
まま母は何をしているのか。
彼女は、訪れる客ひとりひとりに、呪いをかけているのだ。
たぶんウオルト・ディズニーは、
闇があるから、光がより輝いて見える、ということを知っていた。
それと同じことをぼくは望んでいるんだろうか。
最後に光のほうへ行くため、敢えていま、闇の中を歩こうと?
ベアトリーチェに導かれたダンテのように?
そうじゃない気がするんだよね。
ぼくはたぶん、光より闇に、調和より混沌に魅かれている。
それは親のせいでも、誰かのせいでもなく、ぼく自身の「性」のせいだ。
認めなければ。
けれど、心のどこかで期待している。
この「闇」が、「世界」を作り変えることを。
あるいは、より「完全」なものにすることを。
ぼく自身の「世界」を。
そういえば6月に公開される「光のほうへ」は面白そうです。
見てみたい。
きょうも朝から仕事です。。
思いつきですが、
「草食系男子」っていうから物事の本質が見えなくなるのかも。
要するに、何百年も女子たちが独占してきた「愛される者としての立場」を、
奪い返そうと考える一部の男子たちの「反抗」のあらわれなのでは?
なんてことを、ゾンバルトの「恋愛と贅沢と資本主義」を読みながら思いました。
この本についてはまた後で書きます。
思いつきですが、
「草食系男子」っていうから物事の本質が見えなくなるのかも。
要するに、何百年も女子たちが独占してきた「愛される者としての立場」を、
奪い返そうと考える一部の男子たちの「反抗」のあらわれなのでは?
なんてことを、ゾンバルトの「恋愛と贅沢と資本主義」を読みながら思いました。
この本についてはまた後で書きます。
きょうの日経新聞夕刊によれば、アニメやファンタジーと言ったいわゆる「ポップカルチャー」が、震災を機に変わりつつあるという。記事によれば、「現実の惨禍を前にアニメは無力」であり、「人々の関心が現実にある」以上、作り手もその影響を受けざるをえず、現実を反映したテーマ性の強い作品に移行せざるを得ない、という。記事は見出しでそれを「逃避の終わり」と記している。
でも、本当にそうか?
我々はいま、「震災の後」という、いわば「ダークファンタジー」のさ中にいる。それは、あくまでもカギカッコつきの「現実」でしかない。でも、いずれ、圧倒的な現実が襲ってくる。テレビカメラがやってこない被災地。見えない放射能との、果てしなく続く戦い。そんな時、「逃避」の場を持たずに我々は生きていけるだろうか?
ぼくらに必要なのは、今以上に造り込まれた「逃避の場」なのではないだろうか。
物語の中だけで人は生きていけない。いずれ現実に還らねばならない。だからこそ、つかの間の「逃避」の場が必要なんだと思う。がれきだらけの現実を、きらきらした宝の山に変える、「逃避」の物語が。何千年も、人はそうやって生きてきたんだと思う。だって、この震災だけが、人々に訪れた苦難では決してないのだから。
「物語」の時代がきっと来る。ずっと、忘れ去られていたような、「物語の時代」が。みんなを遠くに連れ去ることが出来る、逃避の物語の時代が。
でも、本当にそうか?
我々はいま、「震災の後」という、いわば「ダークファンタジー」のさ中にいる。それは、あくまでもカギカッコつきの「現実」でしかない。でも、いずれ、圧倒的な現実が襲ってくる。テレビカメラがやってこない被災地。見えない放射能との、果てしなく続く戦い。そんな時、「逃避」の場を持たずに我々は生きていけるだろうか?
ぼくらに必要なのは、今以上に造り込まれた「逃避の場」なのではないだろうか。
物語の中だけで人は生きていけない。いずれ現実に還らねばならない。だからこそ、つかの間の「逃避」の場が必要なんだと思う。がれきだらけの現実を、きらきらした宝の山に変える、「逃避」の物語が。何千年も、人はそうやって生きてきたんだと思う。だって、この震災だけが、人々に訪れた苦難では決してないのだから。
「物語」の時代がきっと来る。ずっと、忘れ去られていたような、「物語の時代」が。みんなを遠くに連れ去ることが出来る、逃避の物語の時代が。
びっくりしました。
これでテロのリスクが低下するって、そんな簡単なものなんだろうか。
マーケットはそう考えてるみたいだけど。
思ったんですが、勉強できる人も、ファッションに詳しい人も、
例えば鉄道のダイヤなら誰よりも詳しい人も、レストランに詳しい人も、
みんな同じように互いが互いをリスペクトし合えるような、
そんなシステムは作り出せないだろうか。
ドラクエみたいな「パーティー」を組むとか、リアルの世界で。
なんかね、もう「雑学王」じゃないと思うんだよね。
そうじゃない、各人が各人のありようでリスペクトされる仕組みを作りたい。
大学の頃、文章を見てもらってる人がいて、その人に
「ぼくはとんがった文章というものは“躁状態の文章”か“鬱状態の文章”か
どちらかだと思う、きみのは躁状態の文章としてイケてると思うからこのまま
行きなさい」
って言われて、すっかりその気になってしまった。
たぶんぼくは、今でもその言葉の影響を受けている。
仕事をする時、企画書を書く時、あるいは何かに向き合う時、
ぼくは自分の内面に「擬似的躁状態」を作り上げている気がする。
外見は極めてテンションが低いんだけど、内面だけはやたらテンションが高いという、
とてつもないアンバランスな状態。
対象と向き合ってる時はいいけど、そうでない時は底、みたいな。
今まではそれで何とかやってきた。
嵐のような時間を通り過ぎて、何もしてない時間に戻れば、
ぼくはただただテンションの低い「抜け殻」でいられたから。
でも、今、何もしてない時間がほとんどない。
ずっと揺れてる感じ。
ちょっとバランスが崩れてきてる気がする…。
この本、タイトルに惹かれて買いました。
タイトルって重要ですよね。
これでテロのリスクが低下するって、そんな簡単なものなんだろうか。
マーケットはそう考えてるみたいだけど。
思ったんですが、勉強できる人も、ファッションに詳しい人も、
例えば鉄道のダイヤなら誰よりも詳しい人も、レストランに詳しい人も、
みんな同じように互いが互いをリスペクトし合えるような、
そんなシステムは作り出せないだろうか。
ドラクエみたいな「パーティー」を組むとか、リアルの世界で。
なんかね、もう「雑学王」じゃないと思うんだよね。
そうじゃない、各人が各人のありようでリスペクトされる仕組みを作りたい。
大学の頃、文章を見てもらってる人がいて、その人に
「ぼくはとんがった文章というものは“躁状態の文章”か“鬱状態の文章”か
どちらかだと思う、きみのは躁状態の文章としてイケてると思うからこのまま
行きなさい」
って言われて、すっかりその気になってしまった。
たぶんぼくは、今でもその言葉の影響を受けている。
仕事をする時、企画書を書く時、あるいは何かに向き合う時、
ぼくは自分の内面に「擬似的躁状態」を作り上げている気がする。
外見は極めてテンションが低いんだけど、内面だけはやたらテンションが高いという、
とてつもないアンバランスな状態。
対象と向き合ってる時はいいけど、そうでない時は底、みたいな。
今まではそれで何とかやってきた。
嵐のような時間を通り過ぎて、何もしてない時間に戻れば、
ぼくはただただテンションの低い「抜け殻」でいられたから。
でも、今、何もしてない時間がほとんどない。
ずっと揺れてる感じ。
ちょっとバランスが崩れてきてる気がする…。
この本、タイトルに惹かれて買いました。
タイトルって重要ですよね。
って、休めたことあったんだろうか。
勿論ことしもまる一日休める日はないのだけれど、
ずっとそうだったのかな…と思って。
確かめようにも手帳とか取っておいてないし。
と考えるって、日記をまめに書くって重要ですね。
雨が降ったのなら、「雨が降った」と書きなさい、って
ボブ・グリーンの言葉があるけれど、
何もなかったのなら、「何もなかった」と書くことが大事なのかも。
自分自身にとって。
言葉と言えば、ロラン・バルトの言葉で、
「恋する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」
っていうのがあるけれど、あれって
「( )する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」
ってことなんじゃないかな。
( )の中は取り替え可能で。例えば、
「(仕事)する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」でも、
「(飲酒)する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」でもいいのでは。
根本的には( )の中には、狂気の対象が入るんだから。
( )に「恋」を当てはめると、何だか違ってくる気がする。
( )に入るモノは、言語化不可能なものなんじゃないだろうか。
最近、この10年くらいの自分を振り返ってみて、
ぼくは自分がどこからか、ずっとこの状態な気がしてならないんです。
「( )する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」
そんな状態。病院に行こうにも、( )の中が言語化出来ないのだから、
治しようがない。大体治すことなど望んでないのだし。
最近、仕事でさまざまなものを言語化、システム化しなくてはならないことが多くて、それとは別の「言語化できない自分の状況」が、どんどん日々の生活から乖離してゆくのを感じるんです。これってみんなそうですか?震災の影響?それとも?
そんなわけで、自分の状況の整理のために、思いつきをなるべくまめに書き連ねてゆこうと思います。
勿論ことしもまる一日休める日はないのだけれど、
ずっとそうだったのかな…と思って。
確かめようにも手帳とか取っておいてないし。
と考えるって、日記をまめに書くって重要ですね。
雨が降ったのなら、「雨が降った」と書きなさい、って
ボブ・グリーンの言葉があるけれど、
何もなかったのなら、「何もなかった」と書くことが大事なのかも。
自分自身にとって。
言葉と言えば、ロラン・バルトの言葉で、
「恋する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」
っていうのがあるけれど、あれって
「( )する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」
ってことなんじゃないかな。
( )の中は取り替え可能で。例えば、
「(仕事)する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」でも、
「(飲酒)する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」でもいいのでは。
根本的には( )の中には、狂気の対象が入るんだから。
( )に「恋」を当てはめると、何だか違ってくる気がする。
( )に入るモノは、言語化不可能なものなんじゃないだろうか。
最近、この10年くらいの自分を振り返ってみて、
ぼくは自分がどこからか、ずっとこの状態な気がしてならないんです。
「( )する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」
そんな状態。病院に行こうにも、( )の中が言語化出来ないのだから、
治しようがない。大体治すことなど望んでないのだし。
最近、仕事でさまざまなものを言語化、システム化しなくてはならないことが多くて、それとは別の「言語化できない自分の状況」が、どんどん日々の生活から乖離してゆくのを感じるんです。これってみんなそうですか?震災の影響?それとも?
そんなわけで、自分の状況の整理のために、思いつきをなるべくまめに書き連ねてゆこうと思います。
そんな気分。
久しぶりに宮沢賢治を読み返す。
「オッベル」なんですね。
ずっと「オッぺル」だと思ってた。
「ぱでぃ」と「ばでぃ」みたいなもんか。
「苦しいです、サンタマリア」
ああ、そうだね。
みんな苦しいんだよね。
幸福も不幸も、コントロールできない感情の揺れを
体験しなければならない、という点では等価だと思う。
身に余る幸福も、受け止められないくらいの不幸も、
結局はおなじくらい苦しい。
幸福も不幸もないところへ行きたい。
心静かに暮らしたい。
久しぶりに宮沢賢治を読み返す。
「オッベル」なんですね。
ずっと「オッぺル」だと思ってた。
「ぱでぃ」と「ばでぃ」みたいなもんか。
「苦しいです、サンタマリア」
ああ、そうだね。
みんな苦しいんだよね。
幸福も不幸も、コントロールできない感情の揺れを
体験しなければならない、という点では等価だと思う。
身に余る幸福も、受け止められないくらいの不幸も、
結局はおなじくらい苦しい。
幸福も不幸もないところへ行きたい。
心静かに暮らしたい。
未来はやってこない。
すべては、現在の積み重ねに過ぎない。
できなかったことが、何の前触れもなく、
突然出来るようになったりは、普通しない。
情けないくらい「出来ない」現在の自分を、
気も遠くなるくらいに愚直に積み上げて、
ようやく少しは「まし」な自分が出来てくる。
たまたま見た大リーグのドキュメントで、
才能だけで野球をやってそうに見える4番バッターが、
「どうすれば打てるのか?」と問われて、
「練習しかない。バットのスピードは、振れば振るほど速くなる」
って答えていた。
「現在」しかない。「未来」はやってこない。
だからこそ、「現在」を。
すべては、現在の積み重ねに過ぎない。
できなかったことが、何の前触れもなく、
突然出来るようになったりは、普通しない。
情けないくらい「出来ない」現在の自分を、
気も遠くなるくらいに愚直に積み上げて、
ようやく少しは「まし」な自分が出来てくる。
たまたま見た大リーグのドキュメントで、
才能だけで野球をやってそうに見える4番バッターが、
「どうすれば打てるのか?」と問われて、
「練習しかない。バットのスピードは、振れば振るほど速くなる」
って答えていた。
「現在」しかない。「未来」はやってこない。
だからこそ、「現在」を。
・ぼくはコロッケに弱いらしい。
いろいろメニューがあってもコロッケがあると
ついついそっちに行ってしまう…。
食べ終わるとそんなに印象に残ってないのに。
何でだ??
・考えてみれば、「世界の終わり」はずっと前に始まっている。
世界が始まったときから。
そう考えれば、何も怖くない。
いろいろメニューがあってもコロッケがあると
ついついそっちに行ってしまう…。
食べ終わるとそんなに印象に残ってないのに。
何でだ??
・考えてみれば、「世界の終わり」はずっと前に始まっている。
世界が始まったときから。
そう考えれば、何も怖くない。
「ぼくと契約して××になってよ」
2011年4月23日 日常
っていうのが流行語になっているそうで、その元ネタであり、娘が目を輝かせて魅力を語った「魔法少女まどか☆マギカ」を見ました。娘の学校では随分前から大ブームを巻き起こしてたそうですが…。
すみません、正直ナメてました。「魔法少女」というタイトルからは想像もつかない、ダークファンタジーとしての完成度の高さ。画の新しさ、深夜アニメとは思えない緻密さ。個人的にはエヴァンゲリオンよりハマってしまいました。
結局ヒットする作品って、時代と重なり、時代を先取りしてるんだと思います。
「魔法少女まどか☆マギカ」は、ひとことで言えば、「祈りの物語」です。キーワードは、「もう絶望する必要なんて、ない」。あんまり書くとただのオタクなのがバレるのでこのくらいにしておきますが、ホントに、日本のアニメって油断ならないです。DVD欲しいかも。
すみません、正直ナメてました。「魔法少女」というタイトルからは想像もつかない、ダークファンタジーとしての完成度の高さ。画の新しさ、深夜アニメとは思えない緻密さ。個人的にはエヴァンゲリオンよりハマってしまいました。
結局ヒットする作品って、時代と重なり、時代を先取りしてるんだと思います。
「魔法少女まどか☆マギカ」は、ひとことで言えば、「祈りの物語」です。キーワードは、「もう絶望する必要なんて、ない」。あんまり書くとただのオタクなのがバレるのでこのくらいにしておきますが、ホントに、日本のアニメって油断ならないです。DVD欲しいかも。
結局は「切り取り方」がすべてなんじゃないか?
「細部」なんてあまり気にされていない。
ダヴィンチの画が細部まで描かれていなかろうが、
モナリザが未完成であろうがなかろうが、
見ている人はダヴィンチの切り取る「世界観」に敬服し、感動する。
過度のこだわりは作り手の自己満足に過ぎない。
15分のVTRを10分に縮めるディレクターは、
「仕事をした」つもりかもしれないけれど、
その行為が作品にとってよかったかどうか、確かめる術はない。
同時に2つを見比べることは出来ないからね。
いったい、作品をつくることにおいて何が正しいんだろうか。
「細部」なんてあまり気にされていない。
ダヴィンチの画が細部まで描かれていなかろうが、
モナリザが未完成であろうがなかろうが、
見ている人はダヴィンチの切り取る「世界観」に敬服し、感動する。
過度のこだわりは作り手の自己満足に過ぎない。
15分のVTRを10分に縮めるディレクターは、
「仕事をした」つもりかもしれないけれど、
その行為が作品にとってよかったかどうか、確かめる術はない。
同時に2つを見比べることは出来ないからね。
いったい、作品をつくることにおいて何が正しいんだろうか。
なぜ企画書を書くか、と言えば、それは
「まだ形になっていないものを言語化する」ためだと思う。
考えてみれば、それって「就職活動」に似てる。
企業は、学生の「現在」ではなく、「未来の可能性」を買う。
そのことを理解出来て、企業に対して、
「未来の自分」を言語化することが出来た学生が、
「就職活動」の勝者になる。
ひとにぎりの「体育会系」や「即戦力」を除いて。
「未来の自分」を言語化するには、場数を踏む必要がある。
トライ&エラーを繰り返して、「空気」が読めるようになる。
「企業」が求めているモノがわかるようになる。
企画書も、それと同じだ。
トライ&エラーを繰り返して、「空気」が読めるようになる。
「人々」が求めているモノがわかるようになる。
書き続けるしかない。
…やっぱ合宿でもするか。
「まだ形になっていないものを言語化する」ためだと思う。
考えてみれば、それって「就職活動」に似てる。
企業は、学生の「現在」ではなく、「未来の可能性」を買う。
そのことを理解出来て、企業に対して、
「未来の自分」を言語化することが出来た学生が、
「就職活動」の勝者になる。
ひとにぎりの「体育会系」や「即戦力」を除いて。
「未来の自分」を言語化するには、場数を踏む必要がある。
トライ&エラーを繰り返して、「空気」が読めるようになる。
「企業」が求めているモノがわかるようになる。
企画書も、それと同じだ。
トライ&エラーを繰り返して、「空気」が読めるようになる。
「人々」が求めているモノがわかるようになる。
書き続けるしかない。
…やっぱ合宿でもするか。
ラカンによれば「言語は現実を語れない」。
ところが同時に人は「言語でしか現実を語れない」。
そして彼は、「語りえない現実」を「現実界」、
「言語によって語られる現実」を「象徴界」と名づけた。
人は、「言語」を用いる限り、「現実界」にはたどりつけない。
しかし、時に垣間見てしまったり、触れてしまったりすることがある。
たとえばそれは、「狂気の中にいる者」である。
プラトンの著作を読んでいると、彼がほとんど同じことを言っていることに気づかされる。
紀元前400年。ラカンのおよそ2375年前に、同じようなテーゼが語られてるのって、ちょっと衝撃的。
「ひとつの技術を文字の中に書き残したと思い込んでいる人、また、書かれたものの中から何か明瞭で確実なものを掴みだすことが出来ると信じている人、こういう人たちは皆大変なお人好しである。なぜなら彼らは、書かれた言葉というものが、書物に取り扱われる事柄について知識を持っている人にそれを思い出させるという役割以上に、もっと何か多くのことをなしうると思っているからだ」 (プラトン「パイドロス」)
プラトンは、「言葉」というものが「道具」に過ぎず、「世界そのもの」を描き出すことは出来ない、と言っている。
「魔術的リアリズム」という本の中で引用されている1915年のキリコの言葉も、たぶん同じことを言おうとしているのだと思う。
「すべての事物はふたつの局面を持っている。ひとつは、私たちが日ごろ見ており、人々が一般に見慣れている局面であるところの日常的局面であり、もうひとつは、ごく稀な個人が幻視や形而上的抽象の瞬間にしか見ることの出来ない、妖怪的もしくは形而上的局面である」 (種村季弘「魔術的リアリズム」)
前者をラカンがいう「象徴界」、後者を「現実界」と考えれば合点がゆく。
今回の震災を機に、「現実界」の裂け目が露わになってきている気がする。
それを描きたい。覗き込めるだろうか、ぼくは。狂気に飲み込まれずに。
ところが同時に人は「言語でしか現実を語れない」。
そして彼は、「語りえない現実」を「現実界」、
「言語によって語られる現実」を「象徴界」と名づけた。
人は、「言語」を用いる限り、「現実界」にはたどりつけない。
しかし、時に垣間見てしまったり、触れてしまったりすることがある。
たとえばそれは、「狂気の中にいる者」である。
プラトンの著作を読んでいると、彼がほとんど同じことを言っていることに気づかされる。
紀元前400年。ラカンのおよそ2375年前に、同じようなテーゼが語られてるのって、ちょっと衝撃的。
「ひとつの技術を文字の中に書き残したと思い込んでいる人、また、書かれたものの中から何か明瞭で確実なものを掴みだすことが出来ると信じている人、こういう人たちは皆大変なお人好しである。なぜなら彼らは、書かれた言葉というものが、書物に取り扱われる事柄について知識を持っている人にそれを思い出させるという役割以上に、もっと何か多くのことをなしうると思っているからだ」 (プラトン「パイドロス」)
プラトンは、「言葉」というものが「道具」に過ぎず、「世界そのもの」を描き出すことは出来ない、と言っている。
「魔術的リアリズム」という本の中で引用されている1915年のキリコの言葉も、たぶん同じことを言おうとしているのだと思う。
「すべての事物はふたつの局面を持っている。ひとつは、私たちが日ごろ見ており、人々が一般に見慣れている局面であるところの日常的局面であり、もうひとつは、ごく稀な個人が幻視や形而上的抽象の瞬間にしか見ることの出来ない、妖怪的もしくは形而上的局面である」 (種村季弘「魔術的リアリズム」)
前者をラカンがいう「象徴界」、後者を「現実界」と考えれば合点がゆく。
今回の震災を機に、「現実界」の裂け目が露わになってきている気がする。
それを描きたい。覗き込めるだろうか、ぼくは。狂気に飲み込まれずに。
・脳がつるつるになった夢を見て飛び起きた。いけないいけない。スランプもここまで来ると深刻だ…。でも、ここ数日読んだ本の中から、いくつかヒントのようなものを得られた。
・ブルータス最新号「糸井重里特集」。読めば読むほど糸井さんって深い…。論理展開がすごくソクラテス(というかプラトンの本に出てくるソクラテス)に似てる。この本でもいろいろ刺激的な発言があったけど、中でもぐっと来たのは、「業界の心配するより自分の心配をしろ」ってとこ。「主語を私たちにするから話がややこしくなるのであって、まず主語を私にして考えろ」みたいなことを言ってて、あたりまえのことなんだけど最近陥ってたひとつめの罠に気づかされた。そうだよね。「私たちに何が出来るか」ではなく、「私に何が出来るか」。すべてはその延長線上にある。「私たち」で考え過ぎていた、これがぼくのスランプの原因その1。
・その本の中で鶴見俊輔さんの「神話的時間」の概念が紹介されてて、「コレ昔買った!」と思って本棚から引っ張り出して読んだ。要するに、近代の時間ではなく、物語の時間。「旧約聖書の本文に流れている時間を、いまの私がいる時間の流れで読んでも意味が全然違うんじゃないか?」という疑問から、鶴見さんは「感じることや生きることが言葉と分離する以前の状態」を「神話的時間」と呼んでいる。この考え方もぐっと来た。ぼくも最近「締め切りまでに!」「何とか時間内に!」という「近代の時間」にとらわれ過ぎていて、「神話的時間」の中に魂が行ってなかった。以上スランプの原因その2.
・そして最も大きなスランプの原因。最近凝ってるプラトンの「パイドロス」を今日読んでたら、ああこれだ!と思う描写があった。この本は前段で愛について、後段で言葉についてソクラテスが語るんだけれど、前段の冒頭で
「自分を恋してくれる人がそばにいても、むしろ自分を恋していない人に身をまかせた方がいい、なぜなら恋する人は狂気の中にあるが、恋してない人は正気だから!」
という、とあるソフィストの主張を聴いた人が、ソクラテスに興奮してそのことを告げる、するとソクラテスは、いろいろ考えてこう反論する。
「もし狂気が悪いことだと無条件に言えるならその通りだろう、しかし、我々の身に起こる数々の善きものの中でも、その最も偉大なるものは、狂気を通じて生まれてくるのである。むろんその狂気は、神から授かって与えられる狂気でなければならないが」
ソクラテス(っていうかプラトン)カッコいい…。考えてみれば最近、あまりにも狂気から遠いところに身を置いていた。企画書も何だか手わざで書いていただけな気がする。もっともっと没頭しよう。狂気を取り戻そう。
「私」を「神話的時間」の中に置き、ゆっくりとゆっくりと「狂気」を呼び起こそう。かつてそうだったように。この日記を書き始めた頃のように。引き返せない道の果てにぽっかり開いた巨大な穴の手前で立ちつくしていた頃のように。そうしなければ、このままぼくはダメになってしまう気がする。このまま終わりたくない。まだ引き返せる。狂気と歓喜と絶望の中に。今なら。
・ブルータス最新号「糸井重里特集」。読めば読むほど糸井さんって深い…。論理展開がすごくソクラテス(というかプラトンの本に出てくるソクラテス)に似てる。この本でもいろいろ刺激的な発言があったけど、中でもぐっと来たのは、「業界の心配するより自分の心配をしろ」ってとこ。「主語を私たちにするから話がややこしくなるのであって、まず主語を私にして考えろ」みたいなことを言ってて、あたりまえのことなんだけど最近陥ってたひとつめの罠に気づかされた。そうだよね。「私たちに何が出来るか」ではなく、「私に何が出来るか」。すべてはその延長線上にある。「私たち」で考え過ぎていた、これがぼくのスランプの原因その1。
・その本の中で鶴見俊輔さんの「神話的時間」の概念が紹介されてて、「コレ昔買った!」と思って本棚から引っ張り出して読んだ。要するに、近代の時間ではなく、物語の時間。「旧約聖書の本文に流れている時間を、いまの私がいる時間の流れで読んでも意味が全然違うんじゃないか?」という疑問から、鶴見さんは「感じることや生きることが言葉と分離する以前の状態」を「神話的時間」と呼んでいる。この考え方もぐっと来た。ぼくも最近「締め切りまでに!」「何とか時間内に!」という「近代の時間」にとらわれ過ぎていて、「神話的時間」の中に魂が行ってなかった。以上スランプの原因その2.
・そして最も大きなスランプの原因。最近凝ってるプラトンの「パイドロス」を今日読んでたら、ああこれだ!と思う描写があった。この本は前段で愛について、後段で言葉についてソクラテスが語るんだけれど、前段の冒頭で
「自分を恋してくれる人がそばにいても、むしろ自分を恋していない人に身をまかせた方がいい、なぜなら恋する人は狂気の中にあるが、恋してない人は正気だから!」
という、とあるソフィストの主張を聴いた人が、ソクラテスに興奮してそのことを告げる、するとソクラテスは、いろいろ考えてこう反論する。
「もし狂気が悪いことだと無条件に言えるならその通りだろう、しかし、我々の身に起こる数々の善きものの中でも、その最も偉大なるものは、狂気を通じて生まれてくるのである。むろんその狂気は、神から授かって与えられる狂気でなければならないが」
ソクラテス(っていうかプラトン)カッコいい…。考えてみれば最近、あまりにも狂気から遠いところに身を置いていた。企画書も何だか手わざで書いていただけな気がする。もっともっと没頭しよう。狂気を取り戻そう。
「私」を「神話的時間」の中に置き、ゆっくりとゆっくりと「狂気」を呼び起こそう。かつてそうだったように。この日記を書き始めた頃のように。引き返せない道の果てにぽっかり開いた巨大な穴の手前で立ちつくしていた頃のように。そうしなければ、このままぼくはダメになってしまう気がする。このまま終わりたくない。まだ引き返せる。狂気と歓喜と絶望の中に。今なら。
・企画書を書いてたらあたまの悪い子みたいな文章になってしまって、
自分に失望してしまいました。そんな4月の始まりです。
・そろそろ気分を変えたいんだけど桜を見に行く気にもならない。
人生で桜を見られるのって数十回しかないのに…。
髪でも切りに行こう。
・アメリカの新聞に「東京の人間はどうして自粛ムードなんだ!それで被災者と連帯していると思ったら大間違いだ!お前らは何も生み出していない!」みたいなことが書いてあって。その通りかもな~と思っていたら、「日本人には喪に服するって伝統があるんだ!そういう文化も知らずに勝手なこと言うな!喪が明けたら見返してやるからな!」みたいなことを言い返してる日本人がいて、おっ!と思ったりしています。どっちも正しい気がする。でも、目の前にアメリカ人がいて前段のようなことを言われたら、ぼくは絶対後段みたいなこと言い返せないだろうな~と思うと、強くならなくちゃな、とは思います。あたまも、心も。
・「マジックリアリズム」にこの状況を脱却するヒントがある気がしてこの本を買ったのですが、絵画の話でした…。でもどこにヒントがあるかわからないので読んでみようと思います。
・OASISの“let there be love ”っていい曲ですね。
May all your dreaming fill the empty sky
But if it makes you happy Keep on clapping
Just remember I’ll be by your side
And if you don’t let go it’s gonna pass you by
ってとこにぐっときました。
・そこに愛がありますように。
自分に失望してしまいました。そんな4月の始まりです。
・そろそろ気分を変えたいんだけど桜を見に行く気にもならない。
人生で桜を見られるのって数十回しかないのに…。
髪でも切りに行こう。
・アメリカの新聞に「東京の人間はどうして自粛ムードなんだ!それで被災者と連帯していると思ったら大間違いだ!お前らは何も生み出していない!」みたいなことが書いてあって。その通りかもな~と思っていたら、「日本人には喪に服するって伝統があるんだ!そういう文化も知らずに勝手なこと言うな!喪が明けたら見返してやるからな!」みたいなことを言い返してる日本人がいて、おっ!と思ったりしています。どっちも正しい気がする。でも、目の前にアメリカ人がいて前段のようなことを言われたら、ぼくは絶対後段みたいなこと言い返せないだろうな~と思うと、強くならなくちゃな、とは思います。あたまも、心も。
・「マジックリアリズム」にこの状況を脱却するヒントがある気がしてこの本を買ったのですが、絵画の話でした…。でもどこにヒントがあるかわからないので読んでみようと思います。
・OASISの“let there be love ”っていい曲ですね。
May all your dreaming fill the empty sky
But if it makes you happy Keep on clapping
Just remember I’ll be by your side
And if you don’t let go it’s gonna pass you by
ってとこにぐっときました。
・そこに愛がありますように。
電車はすいていました。
みんな東京を離れ始めているようです。
こんなこと初めてです。
エヴァンゲリオンの世界が本当になったようで。
夜中、眠れなくて、ネットをうろうろしていたら、
こんな文章に出会いました。
心動かされました。
http://niiza.rikkyo.ac.jp/news/2011/03/8549/
ぼくには何が出来るんだろう。
何をなすべきなんだろう。
みんな東京を離れ始めているようです。
こんなこと初めてです。
エヴァンゲリオンの世界が本当になったようで。
夜中、眠れなくて、ネットをうろうろしていたら、
こんな文章に出会いました。
心動かされました。
http://niiza.rikkyo.ac.jp/news/2011/03/8549/
ぼくには何が出来るんだろう。
何をなすべきなんだろう。
配給のカロリーメイトを食べながら作業してます。
高層階だからずっと船に乗ってるみたいです…。
しかしすごかったですね…。
生まれて初めての体験でした。
皆様のご無事をお祈りしております。
高層階だからずっと船に乗ってるみたいです…。
しかしすごかったですね…。
生まれて初めての体験でした。
皆様のご無事をお祈りしております。
What the Hell
2011年2月24日 日常
いい曲だ~。
「どーでもいいのよ」みたいな意味らしいですが。
If you love me
If you hate me
You can’t save me
ってとこがすごくイイ。
たぶんぼんやり聴いてると
You can save me
って聞こえてしまうのは確信犯?
勝ち続けることは難しい。
問題は負けた後どう立て直すか。
だけど負けた後の疲れ方ってハンパないね…。
全身全霊で疲れ切ってるこの感じ。
久しぶりに味わった。
もう負けたくない。
「どーでもいいのよ」みたいな意味らしいですが。
If you love me
If you hate me
You can’t save me
ってとこがすごくイイ。
たぶんぼんやり聴いてると
You can save me
って聞こえてしまうのは確信犯?
勝ち続けることは難しい。
問題は負けた後どう立て直すか。
だけど負けた後の疲れ方ってハンパないね…。
全身全霊で疲れ切ってるこの感じ。
久しぶりに味わった。
もう負けたくない。
電気毛布ひざから掛けながら仕事してます。
仕事でエコに関する調べ物をしてたら
表題の本が出てきたんですが、
「地球最後の日のための種子」。
いいタイトルですよね…。
ついつい衝動買いしてしまいました。
明日を越えれば少しだけ落ち着けそう。
読まなきゃいけない本や衝動買いしてしまった本が
(いまぼくは“アマゾン依存”みたいです…)
目の前に山のように積み上げられてるけど
この1か月くらいずっと仕事ばっかりしてきたから、
少し外に出て友だちに会ったりしたいです。
あと、ひとりでふらっと関西とか九州とか行ったりしたい。
無理かな…。
仕事でエコに関する調べ物をしてたら
表題の本が出てきたんですが、
「地球最後の日のための種子」。
いいタイトルですよね…。
ついつい衝動買いしてしまいました。
明日を越えれば少しだけ落ち着けそう。
読まなきゃいけない本や衝動買いしてしまった本が
(いまぼくは“アマゾン依存”みたいです…)
目の前に山のように積み上げられてるけど
この1か月くらいずっと仕事ばっかりしてきたから、
少し外に出て友だちに会ったりしたいです。
あと、ひとりでふらっと関西とか九州とか行ったりしたい。
無理かな…。